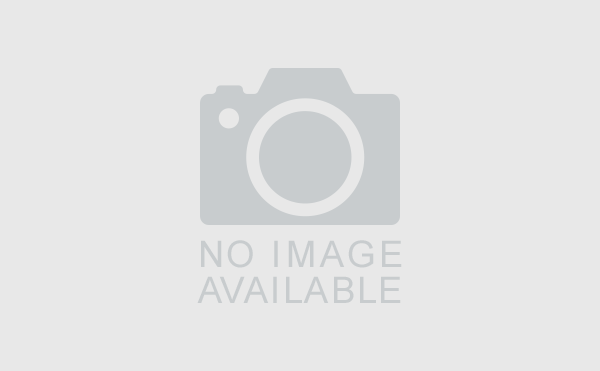非公開会社における議決権行使代理人の資格制限とその限界について(東京高判R4.6.22)
本件(東京高判R4.6.22)は、非公開会社Yの株主Xが、定款の規定に基づいて代理人(弁護士)による株主総会への出席を拒否されたことが、会社法310条1項および831条1項1号に違反すると主張し、株主総会決議の取消しを求めた事案です。争点は、定款において「議決権行使の代理人は当会社の株主に限る」とする定め(以下「本件規定」)がある場合に、株主が弁護士を代理人に選任して株主総会に出席させることを会社が拒否できるかという点でした。
原審(東京地判R3.11.25)は、「会社が弁護士の総会出席・議決権行使を拒否したことは、総会が当該弁護士により攪乱され株主の共同の利益が害されるおそれがあるなど特段の事情がない限り、会社法310条1項に違反する」とXの請求を認め、決議を取り消しました。
本判決も、ほぼ原判決を引用し、控訴を棄却しました(高裁判決、4頁以下)。
この判断から導かれる実務上のポイントは、以下のとおりです。
- 定款によって代理人資格に制限を設けることは原則許されるが、その制限が過度であると議決権行使の機会を実質的に奪うことになり、違法となる可能性がある。
- 代理人が弁護士であり、かつ総会を攪乱するおそれがないことが明白である場合には、代理行使を拒否する正当な理由にはならないと判断された。
- 「特段の事情」がない限り、代理人が株主でないことのみを理由に議決権行使を拒否すると、決議の取消し事由になり得る。
最判S43.11.1は、定款による代理人資格の制限が有効であることを認めたものの、その後「制限の合理性」が問題となるケースが増えています。本件もその一例です。定款の文言だけでなく、株主総会における実態、株主間の力関係、代理人の行動実績など、多様な要素を総合的に判断されることになろかと考えられます。
こういうところが法律の面白いところであり、難しいところです。
より詳しく知りたい→株主総会の招集、運営(進行)、事後処理、株主総会決議の争い方については、こちらのサイトをご参照ください