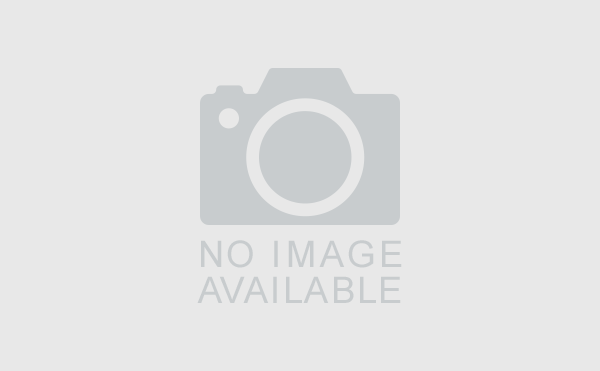役員退職慰労金減額について取締役会が広い裁量権を有するとした判例(最判R6.7.8)
本件(最判R6.7.8)は、甲社の株主総会において元代表取締役Xに対する退任慰労金の支給について社内の内規に従い金額を決定することを取締役会に一任する決議がなされたところ、取締役会がXに対して内規で定められた基準額から大幅に減額された5,700万円が支給するという決議をしたことに対し、Xが内規の誤解釈または裁量権の逸脱があったとして、会社および代表取締役Yに対して損害賠償請求をしたものです。なお、甲社の取締役退任慰労金内規には、退任取締役の退職慰労金は、退任時の報酬月額等により一義的に定まる額を基準とする旨の定めがある一方で、取締役会は、退任取締役のうち、「在任中特に重大な損害を与えたもの」に対し、基準額を減額することができる旨の定めがありました。
第一審及び控訴審は、Xの主張を認め、取締役会が内規の適用を誤り株主総会の一任の趣旨に反する決議を行ったとして、会社と代表取締役の損害賠償責任を認めました。
しかし、本判決は、「本件減額規定は、取締役会は、退任取締役が在任中甲社に特に重大な損害を与えた場合、基準額を減額することができる旨を定めているところ、その趣旨は、取締役を監督する機関である取締役会が取締役の在任中の行為について適切な制裁を課すことにより、甲社の取締役の職務執行の適正を図ることにあるものと解される。甲社の株主総会が退任取締役の退職慰労金について本件内規に従って決定することを取締役会に一任する旨の決議をした場合、取締役会は、退任取締役が本件減額規定にいう「在任中特に重大な損害を与えたもの」に当たるか否か、これに当たる場合に減額をした結果として退職慰労金の額をいくらにするかの点について判断する必要があるところ、上記の本件減額規定の趣旨に鑑みれば、取締役会は、取締役の職務の執行を監督する見地から、当該退任取締役が甲社に特に重大な損害を与えたという評価の基礎となった行為の内容や性質、当該行為によって甲社が受けた影響、当該退任取締役の甲社における地位等の事情を総合考慮して、上記の点についての判断をすべきである。そして、これらの事情は、いずれも会社の業務執行の決定や取締役の職務執行の監督を行う取締役会が判断するのに適した事項であること、さらに、本件内規が本件減額規定による減額の範囲等について何らの定めも置いていないことに照らせば、取締役会は、上記の点について判断するに当たり広い裁量権を有するというべきであり、取締役会の決議に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるということができるのは、この判断が株主総会の委任の趣旨に照らして不合理である場合に限られると解するのが相当である(原審は、本件減額規定は特に重大な損害を与えた在任中の行為によって生じた損害相当額のみを減額し得る旨を定めたものとするが、本件減額規定がそのような趣旨のものであるとは解されない。)。」としたうえで、取締役会はXの過去の複数の不適切な支出行為等(宿泊費の過大受給、報酬の過剰設定、文化芸術活動支出等)を総合的に評価し、広範な裁量の範囲内で判断を行ったと認定しました。さらに、同決議は中立的な調査委員会の詳細な調査報告を踏まえた合理的なプロセスに基づくものであり、取締役会で実質的な議論も尽くされていたことから、裁量権の逸脱や濫用は認められないと結論づけました。
この判例から明らかとなるのは、株主総会による一任決議がなされた場合、取締役会には一定の裁量が認められるものの、その判断が合理的な根拠に基づき、調査と議論を尽くした上で行われていることが強く求められるという点です。特に、慰労金のように取締役の在任中の行為に対する会社としての評価が含まれる場面では、その評価の基準やプロセスの透明性が後に法的評価の対象となります。
取締役の報酬や慰労金をめぐる判断は、会社法上の規律のみならず、株主の期待や真意、取締役会における議論の適切性、企業統治の健全性といった要素とも密接に関連します。本判決は、そのバランスの取り方と取締役会の裁量の範囲を示したものとして、高い意義を持つといえます。こういうところが法律の面白いところであり、難しいところです。
さらに詳しく知りたい!→役員退職金に関する会社法及び税務上の規制については、こちらのサイトをご参照ください。