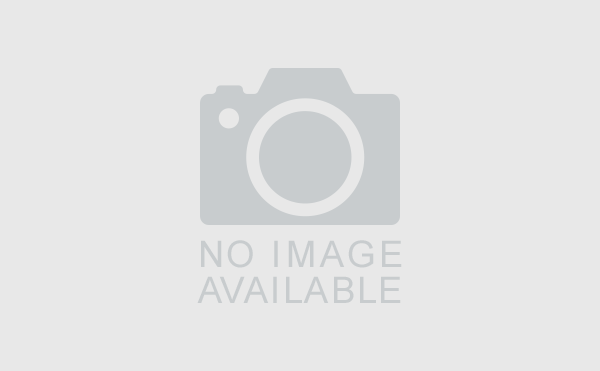労務時間管理に係る取締役らの善管注意義務が問題となった裁判例(福岡高判R4.3.4)
本件(福岡高判R4.3.4)は、甲銀行の株主Xが、甲銀行の元従業員である夫Bが業務に起因して自殺したことに関し、当時の取締役Yらが労働時間管理体制の構築および運用について善管注意義務を怠ったことにより、甲銀行が損害(損害賠償金の支払いや信用毀損)を被ったと主張して、会社法847条の2および423条1項に基づき、株主代表訴訟を提起したものです。
原審は、「労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは周知のところであり、労働基準法所定の労働時間制限や労働安全衛生法65条の2所定の作業管理に関する努力義務は、上記のような危険の発生を防止することをも目的とするものと解されることからすれば、使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負う(最高裁平成12年3月24日第二小法廷判決・民集54巻3号1155頁)。・・・そして、上記使用者の労働者の健康等に対する安全配慮義務を遵守するために、従業員の労働時間管理を含む労務管理は企業経営において不可欠かつ会社経営の根幹に係る重要な事項であると考えられることに加え、使用者は、労働者に対し36協定に基づく時間外労働をさせた場合に労働基準法37条1項に基づく割増賃金を支払う必要があるほか、厚生労働省が定めた労働時間適正把握基準・・・を遵守することが求められていることに照らすと、会社は従業員の健康等に対する安全配慮義務を遵守し、その労務管理において従業員の労働時間を適正に把握するための労働時間管理に係る体制を構築・運用すべき義務を負っており、代表取締役及び労務管理を所掌する会社の取締役も、その職務上の善管注意義務の一環として、上記会社の労働時間管理に係る体制を適正に構築・運用すべき義務を負っているものと解される。また、代表取締役及び労務管理を所掌する取締役以外の取締役は、取締役会の構成員として、上記労働時間管理に係る体制の整備が適正に機能しているか監視し、機能していない場合にはその是正に努める義務を負っているものと解される・・・もっとも、会社が上記労働時間管理に係る体制の構築・運用義務を履行するに際し、具体的にどのような内容の体制を整備すべきかについては、労務管理が専門的な知識や経験を要する業務であることに加え、規模の大きな会社では労務管理のためのシステムの整備に相応の費用及びそれに専従する人員の配置を必要とすることを併せ考慮すると、上記労働時間に係る体制の構築・運用は経営判断の問題であり、会社の経営を委ねられた専門家である代表取締役及び労務管理を所掌する取締役に裁量権が与えられているというべきである。したがって、会社の取締役に対し、適切な労務管理の体制の構築・運用を怠ったことが善管注意義務に違背するとしてその責任を追及するためには、代表取締役及び労務管理を所掌する取締役の判断の前提となった情報の収集、分析、検討が不合理なものであったか、あるいは、その事実認識に基づく判断の過程及び判断内容に明らかに不合理な点があったことを要するものと解するのが相当である(なお、取締役は、会社経営を行うに当たり法令を遵守することが求められているから、取締役が上記労務管理の体制整備に際して労働基準法等の法令を遵守すべきことは当然である。)。」としたうえで、甲銀行における労働時間管理に関する内部統制システムが当時として一定の合理性を有し、「労働時間管理に係る内部統制システムの構築・運用のために行っていた情報収集、分析、検討が不合理なものであったとまではいえないし、上記の改善策を行う旨の判断の過程及び判断内容に明らかに不合理な点があったものともいえないから」として、取締役の善管注意義務違反を否定しました。
控訴審である本判決も、原審の判断を是認し、ほぼ原審を引用したうえで、「平平成24年当時においてA銀行が構築・運用していた労働時間管理に係る体制は相応の合理性を有するものであって、その適正な運用を担保するために複合的・重層的な施策が取られており」などと説示し、控訴を棄却しました。
この裁判例から得られる実務上のポイントは以下のとおりです:
・労働時間管理に関する取締役の善管注意義務の内容は、企業の規模や業種、当時の技術的環境等に照らして相対的に判断されるべきである点。
・内部統制システムの整備に関しては、すべてのリスクを排除する体制を構築する義務までは求められず、一定の合理性と時代状況に適合していれば善管注意義務に違反しないとされうる点。
他の労働災害に関する裁判例と比較すると、本件は、企業側の管理体制に相応の配慮が認められるケースでありながらも取締役の責任が否定された点に特徴があります。従業員の過労や安全配慮義務違反に関しては、企業の対応状況や是正措置の有無が厳格に審査される傾向にありますが、本件のように、内部統制の整備状況や判断過程の合理性が重視されることもあります。
こういうところが法律の面白いところであり、難しいところです。
取締役の内部監統制システム構築義務違反についてはこちらのサイトをご参照ください