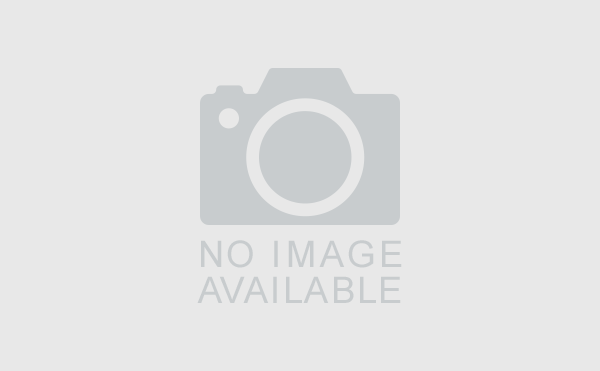地面師(詐欺師)にだまされた場合の取締役の責任が問題となった事例(大阪地裁令和4年5月20日判決・大阪高裁令和4年12月8日判決)
地面師によって、大手不動産会社が騙された事件で、株主代表訴訟により取締役の責任が問われた事件をご紹介します(大阪地裁令和4年5月20日判決・大阪高裁令和4年12月8日判決)。かなり世間を騒がしたので、ご存知の方も多い事件かと思います。もちろん、騙す方が悪いわけですが、騙された方の取締役に善管注意義務ないし忠実義務に違反する任務懈怠があると言えないのかが問題となりました。
本件は、大手住宅メーカー(以下「会社」といいます。)が、実体のない不動産売買を持ちかけられ、詐欺により約55億円もの損害を被ったことをめぐり、株主が当時の代表取締役および取締役に対して会社法423条1項に基づき損害賠償を求めた株主代表訴訟です。問題となった不動産取引は、詐欺グループが虚偽の売買契約や本人確認書類を偽造し、あたかも取引が正当であるかのように装っていたもので、会社は現地視察や稟議を経てこの取引を進め、多額の手付金および残代金を支払いましたが、最終的に登記申請が却下されたことから詐欺が発覚しました。そこで株主Xが、当時の代表取締役Y1および取締役Y2に善管注意義務・忠実義務違反による任務懈怠があったとして株主代表訴訟を提起したのが本件です。
第1審は、「取締役による決裁を経て不動産を購入するに至ったが、それによって当該会社に損害が生じた場合、かかる意思決定に関与した取締役が当該会社に対して善管注意義務違反ないし忠実義務違反による責任を負うか否かについては、取締役に求められる上記の判断が、当該会社の経営状態や当該不動産の購入によって得られる利益等の種々の事情に基づく経営判断であることからすれば、取締役による当時の判断が取締役に委ねられた裁量の範囲に止まるものである限り、結果として会社に損害が生じたとしても、当該取締役が上記の責任を負うことはないと解され、当該取締役の地位や担当職務等を踏まえ、当該判断の前提となった事実等の認識ないし評価に至る過程が合理的なものである場合には、かかる事実等による判断の推論過程及び内容が著しく不合理なものでない限り、当該取締役が善管注意義務違反ないし忠実義務違反による責任を負うことはないというべきである。」としたうえで、要旨、会社が大規模で分業された組織形態をとっていることを前提に、取締役が関与する業務範囲や知識・経験、部下からの報告内容などを踏まえれば、当該取引の判断過程が合理的であり、著しく不合理とまでは評価できないとしてXの請求を棄却しました。控訴審も、原審をほぼ引用して、控訴を棄却しました。
この裁判例から会社法上の善管注意義務・忠実義務の解釈においては、企業規模・組織構造・業務分掌が重要な要素として考慮されることがわかります。特に本件のような詐欺事案では、上場企業のような大規模企業では、当然ですが、取締役個人にすべての判断を求めるのではなく、合理的な業務フローや情報伝達体制に基づいた判断であれば取締役個人の責任を問われにくい傾向があるように感じます。一方で、詐欺を防ぐような内部統制やリスク管理体制を構築する義務に違反しているという点がが問題にはなりますが、株主たる原告が内部統制やリスク管理体制が不十分であることを立証するのは、かなりハードルが高く、一般的には難しいと思われます。
類似の株主代表訴訟として、リスク情報の共有不足や、内部告発の黙殺などが問われた事例(例えばライブドア事件やオリンパス事件)では、結果が異なることもあるため、各事件ごとに事情を丁寧に検討する必要があります。こういうところが法律の面白いところであり、難しいところです。